テオフィルスの『さまざまの技能について』より
 |
大地とは、 建てつつ担うものであり、 養いつつ実らせるものであり、 はぐくむ水源や鉱石、 植物や動物からなる全体である
『有るといえるものへの観入』 |
 |
|
ロマネスク時代の建築や彫刻、あるいは絵画(写本挿画)などを見ていると、これらが素材を通して大地の恵みを大きく受けていることを感じることがある。建築の多くはその土地から採掘される石材に支配され、彫刻や絵画も同様である。近郊に良質の採石地や鉱脈があれば作品に反映される。そうした実例をマリア・ラーハの聖堂に使用されている石材について見てきた。彫刻向きの石材を産するラングドックやポアトゥーでは浮彫彫刻が発展した。
ここでは多種多様の優れた石材を自由に使うことが出来る条件を得た建築家の喜びが感じられる。資金に恵まれれば遠方より石材を取り寄せることもあったが(シュパイアー大聖堂にはアイフェルから運ばれた玄武岩が使用され、マクデブルク大聖堂はラヴェンナから、シント・トルィデンのベネディクト会修道院はライン川経由で柱頭が運ばれてきた)、ゴシック時代には交通網の整備と流通の発展によって「国際化」したのと対照的に例外的であった。これらの素材は人手により手間と時間をかけて原料から素材へと仕上げられる以前、地球史レベルの遥か太古から自然により育まれてきたものである(→粗い石)。ともするとこれらの作品は天文学的な時間をかけて準備された大地に咲き出た花であり、長い熟成の後に(それに比べれば一瞬に過ぎない最後にのみ)人手が介入して「作品」として、遂に完成されたように思えることもある。 建築では以上のようであり石を扱う彫刻も同様であるが絵画ではどうか。初期ロマネスク時代にテオフィルスにより書かれた『さまざまの技能について』(『提要』で知られる)にその答えがあった。『提要』には各色材がどのように作られるかを現代でも追試可能なほど詳細に述べられている。それによると例えば鉱物から精製する顔料は言うに及ばず、金属板を尿や酢に浸したり、植物からとる染料であったり、或いはキャベツなど野菜を使ったりと大地の差し出するものを存分に使用している。
テオフィルス Theophilus 『さまざまの技能について』 De Diversis Artibus
『提要』の翻訳は図版と解説つきで出版されている。 『提要』に登場する色名 |

色名
| Atramentum | 緑礬 | 銅版に熱した酢か尿をかける |
| Auripigmentum | 黄色 | 金の代用色 |
| Calx | 白 | 石灰→炭酸化、CaCO3 |
| Gypsum | 白 | 石膏、CaSO4 |
| Creta | 白 | 炭酸カルシウム、CaCO3 |
| Carmin | 赤 | コチニール(臙脂虫)からとった染料 |
| Cenobrium | 朱 | 硫化水銀、辰砂、HgS |
| Cerosa | 白 | 鉛白、鉛板に熱した酢または尿をかけ1ヶ月放置して白粉を生じさせる |
| Cerosa Flava | 黄色 | マッシコット |
| Croceum | 黄色 | 秋咲きサフランの雌蕊を乾燥させたもの |
| Folium | 紫 | 弱酸性で赤、弱アルカリで紫、強アルカリで青に変化するヘリオトロープの実 |
| Indicum | 紺 | インディゴブルー、インド原産の天然品か代用品か不明。『エグベルトの福音書』でインディゴブルーが確認され、アフリカ産と推測されている |
| Lazur | 群青 | ラピス・ラズリ、当時も現在も唯一の産地はイスラム圏で修道院は交易を通じて入手していた。「天上の青」として紫や金と共に高貴な色とされた。 |
| Menesc | 暗青色 | 植物由来で藍の代用 |
| Minium | 黄赤 | 最も明度の高い赤、Pb3O4、写本挿画を意味する「ミニアチュール」の語源となった |
| Ogra | 黄土 | 天然産水酸化鉄、色は地域色に富み多様、Fe(OH)2 |
| Prasinus | 緑土 | 緑土または緑石英か。画像はマラカイト。 |
| Rubeum | べんがら | 酸化第二鉄、赤さび、Fe2O3 |
| Sucus | 緑 | キャベツ、ねぎ、グラジオラスなどの絞り汁で葉緑素の色 野菜の島でもあるライヒェナウ島産のキャベツ、結球するのは16世紀から |
| Viride | 銅青 | またはスペイン緑Viride Hispanicum、塩基性酢酸銅、(CH3COO)2Cu、蜜を塗って得る説もある |
| Exudra | 暗赤色 | べんがらに少量の黒を混ぜる |
| Lumina | 明肌色 | 肌色Membranaに鉛白を加えハイライトに使う |
| Membrana | 肌色 | 鉛白を焼いたCerona Flavaに鉛白Cerosaと朱Cenobriumを混ぜ、裸体や顔面に使う |
| Posc | 暗赤色 | 肌色にべんがらと朱を混ぜる |
| Rosa | 薔薇色 | 肌色に朱と鉛丹を混ぜる |
| Veneda | 暗灰色 | 黒と白を混ぜ、瞳や壁画の下塗りに使う |
| Album | 白 | 石灰、鉛白、骨粉など |
| Nigrum | 黒 | 葡萄の木から作った木炭かランプの煤から作った墨 |
| Flavus | 赤金色 | 不明 |
| Purpureus | 紫 |
プルプラ貝 purpura haemastomaから抽出した染料でティリアン・パープルとも呼ばれる。ローマ皇帝を象徴する色(ネロは皇帝以外の使用を禁じた)。紫(パープル)の語源で日本の紫からするとかなり赤みがかっている。貝からの抽出(1グラムの染料を得るのに5000個の貝を必要とした)後、複雑な化学的過程を経て染料となる。生産は地中海沿岸のみで行われた。化学成分はdibromoindigotin。 2010年代に入り、西ヨーロッパ各地にある「紫」の写本が相次いで分析された(非破壊分析が可能となったこと、装置がポータブル化され所蔵元に持ち込めるようになった)。ここで、ティリアン特有の臭素が検出されるかどうかが基準になる。分析の結果、従来ティリアン・パープルと思われていた写本(ヴィーン創世記、ロッサーノの福音書など)はほぼ全てティリアンを使用していないことがわかった。 その代わりとして使用されたのは、コチニールが最も多い。   dibromoindigotinを分泌する巻貝 ランバート、中島健訳『遺物は語る』(青土社、1999年)から |
| Saphireus | 青 | 青紫と推定、ガラスの色名に用いている |
| Violaticum | 菫色 | PurpureusまたはSaphireus |
画材
| Verum | 羊皮紙 | 羊または牛皮から作る紙、製作方法が載っていないのは当たり前すぎたたためか。上質の羊皮紙(1000年を経ても色褪せしない見事なもの)は多量の羊から供給可能であることを前提とするので富裕な修道院でないと制作できない(画像は牛の羊皮紙)。 |
| Gummi | 膠 | 亜麻仁油にフォルニスと呼ばれる樹脂(アラビアゴム)を細かく磨って加える。引火に注意 |
| Gummi | 膠 |
ゼラチン*、ちょうざめHusoの浮き袋からとる。ちょうざめは昔も今も黒海産が有名であるが11世紀頃にはボーデン湖にも棲息していた可能性がある *膠はコラーゲンの三重鎖構造を解いたもので骨と皮ではタイプが異なり安定性が変わる |
| Gummi | 膠 | ちょうざめが手に入らないときは、犢皮、鰻(ボーデン湖名物)皮、カワカマスの骨を使う |
| Gummi | 膠 | 鹿の生皮や角からとる。この膠は下塗り用 |
| Gummi | 膠 |
植物由来の樹脂もあった。画像はサンダラク(檜科)の膠 |
| Aureus | 金箔 |
金箔を背景に大量に用いる様式は東ローマでまず行われ、ライヒェナウ派で例外的に採用された。本格的な普及は12世紀以降である。 (1)亜麻布を最も細かいべんがらで擦り光沢が出るまで磨く (2)犢皮で袋をつくる (3)槌で打ち延ばした純金を磨いた亜麻布に交互に挟み犢皮袋に入れる (4)滑かな石上に置き真鍮の槌でたたく 卵白で接着し、象牙などで丁寧に磨く。貼るときは風と息がかからないように注意している。下の例をみると背景と人物の細かな部分まで金箔を貼っている。 カロリング時代の写本は冶金技術が途上だったせいか、金の純度は低い。  |
| Aureus | 金泥 | 純金を乳鉢で微細になるよう砕く。凝集塊を生じないように湿式粉砕で行なう |
| Pseudaureus | 偽金 | 金がないときは錫をサフランで着色させる |
| Ink | インク | さんざしの木片から抽出したタンニンを濃縮し赤熱した鉄棒を入れてタンニン酸鉄とする |
| Gluten | チーズ膠 | 木板接着用で精製したチーズに生石灰を入れる |
彩色例(挿画はいずれもライヒェナウで制作された「皇帝写本」、UNESCOにより「ドキュメントの世界遺産」に登録されている)
|
『バンベルクの黙示録』から 若い女性「太陽をまとう女」の顔、白っぽいハイライトとプラシーヌスを混ぜたシャドウ。髪との境は赤褐色 …鉛白を赤金色に変わるまで焼け。その上でそれを磨り、肉色に似るまで鉛白と朱とを混ぜよ。これらの色の混合は汝の判断によるが、例えば、もし何時が赤い顔を描かんと欲する場合には、更に朱を加えよ。しかして白い場合には白(album)を加えよ。更に蒼白い顔の場合には、朱の代わりに小量のプラシーヌスを加えよ… 髪については 紫の衣裳は本来は皇帝の一族であることを示すが栄光の王や聖女などに逆転用された。プルプラ貝から抽出した染料「プルプレウス」(上記参照)が有名。 |

|
|
『バンベルクの黙示録』から 「栄光の王」を讃える長老たち、上の女性よりも赤みがかっていて白のハイライトを使っていない。松明の炎は金箔の上に書かれている。髪と髭は灰色。 少量の黒を鉛白と混ぜて頽齢者の髪と髭を満たせ。この顔料により多くの黒と少量のべんがらとを加え、それで線を引き、そして純な鉛白で明色を施せ 顔料の調合については |

|
|
『エグベルトの福音書』から 献呈図のボーダー、フォリウムを用いた部分、フォリウムは一つの色素を石灰でpHを変えることにより好みの色調を得る。 またもし紫のフォリウムで、頁にパリウム(枠部分)に似たものを作ることをよしとするならば、石灰を入れずにしめらされた同じ調合液で、まずペンでこの頁に組紐文か渦文を描き、又その内側に、鳥、或いは動物、又は葉飾りを描け。そしてそれが乾いた時に、一面にフォリウムをうすく、ついでより厚く、又もし必要ならば三度目を塗れ。更にその後に汝は、水を入れずに攪拌された古い卵白をその上にうすく塗れ このボーダーではハイライト部分に金彩が、内側に「天国の青」ラピスラズリ、金箔が施された。赤紫色の地の部分は、石灰(アルカリ)によるpH調整で濃淡を変えたフォリウムで着彩されている。 |
 |
| * | 鉛白、鉛丹、臙脂は卵白で調合するよう指示している。 |
| ** | 『ケルズの書』の画家は塩緑の顔料を用いている。塩緑は水があると腐食性の酸になる。後に(写本のかさばりを減らすため誤って)水につけられたことで塩緑を使った部分は羊皮紙を腐食させて孔をあけてしまった。 |
私はあなたを語るつもりだ、私はあなたを観察しよう、
膠塊粘土や金でではなく、林檎の樹皮から取ったインクだけで。
…なぜならあなたは大地だ
リルケ『時祷集』、『修道院生活の書』から(富岡近雄訳)
| Scriptrium |
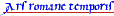



|