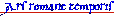「ヘロデ王の宴」のサロメ
オーギュスタン美術館の柱頭彫刻から
|
19世紀末に「ファム・ファータル」として文学や美術に登場したヘロデ王の(義理の)娘、サロメはマルコ及びマタイ福音書に洗礼者ヨハネに関する記事の中で記述されている。聖書では単にヘロデヤの娘とだけ述べられていて名前は出てこない。この王女の名前がサロメであると言及したのはヨセフスの『ユダヤ古代史』が最初であった。サロメは6世紀の写本に最初に現れ、中世にも絵画や彫刻のテーマとなっていた。ルネサンス以前で有名なのはヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂のモザイク(12世紀)やミュスタイルの聖ヨハネ修道院聖堂壁画のアクロバットなサロメである。 |
 |
|
Claustra da San Jon, Müstair, 12c.
|

Basilica di San Marco, Venezia
このモザイクに代表されるように、世紀末まで踊る王女以上の関心が持たれず官能性、ましてや「7つのヴェールの舞」とは無縁である。聖書に「踊って母親の希望に従って首を望んだ」以上の記述がないからもっともな事であるけれども、中世にも例外的な作品が存在する。


『ヘロデの宴』柱頭正面、右側面
Musee Augstin, Toulouse(Cloitre de Saint-Etienne旧在)、12世紀
トゥルーズ周辺の柱頭彫刻を集め、サン・テチエンヌ修道院廻廊旧在だったこの柱頭彫刻はロマネスクラングドック派の傑作の一つとされている。この柱頭ではヨハネの斬首、首を(踊りながら?)受け取りヘロデのもとへ運ぶサロメ(まるでディナーのパスタを運んでいるような感覚であるが)が刻まれている。聖書にはもちろん受け取って運んだことは記述されていない。ここで最も興味深いのは左側面の彫刻で踊り終わったサロメとヘロデ王の場面である。
 |
王妃ヘロデヤ 公主の顔をお見詰めなされては行けませぬ
ヘロデ王 近うまゐれ、撒羅米、近うまゐれ、褒美をとらせう
オスカー・ワイルド、『サロメ』、日夏耽之介訳、講談社文芸文庫p.159, 166
|
ヘロデ王は既に踊り終えたばかりのサロメの顎に手を差し伸べている。中世を通じて通常子供として表現(ヘロデヤよりも小さく表現される)されてきたサロメはここで、ロマネスク彫刻でも珍しいくらい魅力的で官能的に表現され(聖書ではサロメの容姿について全く触れていない)12世紀のこの彫刻家はサロメを19世紀のモローに近い意識で見ているようである。サンテチエンヌの彫刻家だけでなく、カニグーのサン・マルタン修道院の彫刻家は更に大胆である。
 |
 |
 |
| サン・マルタン修道院廻廊の彫刻 |
最も知られたサロメのイメージ、ギュスターヴ・モロー |
ルドンのデッサン |
ローマ時代、小アジアの上流社会の女性は人前で裸になることに抵抗がなく、それどころかステイタス・シンボルのような状態であった。万一、誰かが変な考えを起こして裸の女性に近づいても完璧で厳重なガードに妨げられる。それだけのガードを持てるほど富裕であるという証でもあり、サロメもそうした文化に近い所で生きていたのかもしれない。キリスト教会はこの風習をたいへん嫌って強く非難した。このために長い間キリスト教美術は磔刑でさえ着衣という奇妙な状態が続いた。カニグーの石工がこのような背景を知っていたか不明であるが、重要人物の首を褒美として貰えるほどの踊りとなれば単なるテクニック以上のものがあったことを石に刻み込んでも不思議ではない。修道院の瞑想の場で禁欲の修道士に対し挑発し続けている。

アーヘンのオットー家福音書、アーヘン大聖堂宝物館
サロメに関する資料
オスカー・ワイルド、日夏耽之介訳、ポオ詩集・サロメ、講談社文芸文庫、1995年
井村君江、サロメ図像学、あんず堂、2003年
Romanesque Sculpture, Musee des Augustins-Toulouse, 1999.